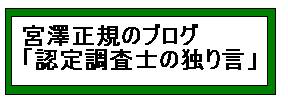|
平成21年8月8日 土地家屋調査士ADRに関する雑感(Ⅲ) 静岡県土地家屋調査士会会員 認定土地家屋調査士 宮 澤 正 規 土地家屋調査士ADRを考える上で法務局(法務省民事二課)がすでに実践している筆界特定制度を無視することはできない。むしろ、筆界特定制度が存在することにより土地家屋調査士ADRが制度としてかろうじてあり得ると解釈したほうが良いのではないかと考える。筆界特定制度が無かった時代は、境界についての争いは境界確定訴訟として(形成訴訟)裁判所に持ち込まれていた。形成訴訟は必ず何らかの形で裁判所が境界を示すこと(判決)が求められていたところでありますが、現実は和解という方法での決着が多かったのではないかと推測します。その当時の境界確定訴訟では土地家屋調査士による鑑定(私鑑定も含む)が相当数形成裁判の判断基準となり多くの土地家屋調査士会で「鑑定人養成講座」と称した研修がひろく行われることとなりました。 そもそも「筆界(ひつかい)」と「境界(きょうかい)」あるいは「公法上の境界」と「所有権界」という詭弁にも似た普通の市民が認識し得る境界とは異なる議論に入っていくことそれ自体が日本国の法制度における瑕疵ではないかと考えます。日本国にとってこれは推測ですが一般市民の境界問題(紛争)は大きな関心事ではないのです。何故ならば、国土は国家のものであり、筆界の多少差異があったとしても徴税の観点から考えればどちらでも良いといった程度の認識でしかないのではないかと思います。 筆界特定訴訟という形成裁判において判事が筆界を形成し判決を下すこと事態、国家にとっては煩わしいことだと考えるのが一般的であったと思います。したがって裁判所にとって法務局が担当する筆界確定制度は本来歓迎されるべきものだったと想像します。しかしながら国は法務局に筆界確定をすることを認めませんでした。理由は様々に述べられていますが、いずれにしても筆界はそもそもどの時代であれ、国が確定した事実(真理ではない)であり神のみぞ知るといったものではないと思います。むしろ、今日において考え得ることは、筆界を本来管理すべき国がそのことを怠ってきたこと、そのことに問題がと原因があるのではないかと考えます。 筆界と所有権界の議論は、実は土地家屋調査士ADRにとっては重要な意味を持ちます。まもなく、筆界特定制度の見直しが議論されようとしています。法務局が筆界特定の分野で「所有権界問題」も扱いたいとの意向があるとの情報に接し土地家屋調査士ADRの終焉を想像するのは私だけでしょうか。 他の隣接法律職種と異なり「認定土地家屋調査士」研修希望者は相当少なく会員全員(全国約18,000人)が認定を取得するのに15年程度の期間を要すると考えられています。 我々土地家屋調査士のADRは民事の問題として捉えられがちですが、実は国そのものの事情を内在しているという特殊な状況であるという認識を法学者始めADR・民間調停を推進することを実践されているインストラクター(指導者)の皆様が理解されているのかと言う素朴な疑問を持つものであります。 境界問題が、国の都合による煩わしい問題としてのくくりから私達国民の問題として議論されていくのか、現実は微妙な状況にあると考えます。私は境界問題(紛争)を単に民事の紛争として捉えることに疑義を持ちます。しかしながら前述したように、たかだか民間の境界紛争は結果として国にとって国土の問題ないしは徴税の問題に至りませんから特に裁判所はできるだけ関わらないと言うスタンスを今後も取り続けると考えます。 以上のような背景がある国家の事情ないしは同様な私的な当事者の事情をふまえた上での境界紛争解決を目指すADR機関を今までほとんどその分野について専門的に考えてこなかった土地家屋調査士が直ちに運営することが可能であるかという現実については疑問を抱かざるを得ません。 |