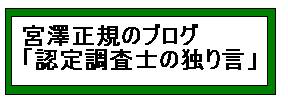|
平成21年8月8日 土地家屋調査士ADRに関する雑感(Ⅳ) 静岡県土地家屋調査士会会員 認定土地家屋調査士 宮 澤 正 規 土地家屋調査士がADR機関(境界問題相談センター)を運営することについてあたかも無謀であるがごとき感想を再三述べているのですが真意は決してそうではありません。むしろ、自分自身が土地家屋調査士であることを含めて土地家屋調査士ADRに将来を託したい、あるいは期待したいというベクトルが働いていることを理解して欲しいと思います。 そもそも土地家屋調査士とは何者なのでしょうか。戦前、土地調査員、家屋調査員と称されて税務署所管の土地台帳、家屋台帳に課税を目的とした調査をしていたものが、戦後になって議員立法による「土地家屋調査士法」の制定により土地家屋調査士と称するようになりさらに登記の一元化(表題部(土地台帳・家屋台帳)と甲区・乙区の合体)によって現在の不動産登記の表題部分を扱うことを業とするようになったものです。すなわち、本来は、不動産に対する課税対象の明確化を目的とした仕事であったわけであり現在もそれを継承していると言って差し支えないと思います。 今日では建物を新築した場合ほとんどの国民が「建物表題登記」を申請しますがはたして何故なのでしょうか。不動産登記法は建物表題登記を始め表題部に変更があった場合一定の期間内に報告(申請)するように定めています。しかしながら必ずしも登記されている事項と現実(現況)が一致しているとは限りません。それよりも、登記がされていない(未登記という)建物が多く存在している現実があります。しかしながら、未登記であることによって市民が課税を免れているのかというと決してそうではありません。むしろ、不動産登記法で言うところの建物として認定しがたいものについても課税されている現状があります。なぜ、現在において未登記建物に対する課税をすることが可能なのでしょうか。先に述べました土地台帳・家屋台帳を市町が継承したことに起因します。現在も市町の課税課に土地係、家屋係が存在し彼らが旧来の土地台帳ないしは家屋台帳に類似した帳簿(不動産課税台帳)の管理をしているのです。 すなわち、土地家屋調査士の業務である不動産登記法に基づく表題登記と司法書士が扱う権利の登記との一元化により、いわゆる課税を目的とした土地係、家屋係の必要性が無くなるといった行政改革ないしは制度改革が表向き前向きになされたように思われてきたのですが、実はほとんど何も変わってはいなかったと言うことが真実です。しかも現在に至っても、法務局は市町の課税課(土地係・家屋係)に対して「税通」と称して登記情報を送っています。つまり、徴税ないしは課税の観点では国(法務局)も市町もタックを組んでいるわけです。つまり端的に述べれば、登記制度は即ち市町の担当する課税・徴税のための補完制度であり決して国民の権利を守る制度とは考え難いのです。なんとなれば、二重売買において先に登記したものが権利を取得しますよ(対抗要件)などという考え方がいかにも登記の最重要事項として述べられていますが根底にあるのは誰が納税義務者となるかと言うことだと考えます。 現在ほとんどの国民が建物表題登記を申請しその後所有権の保存登記をするのは、その先にある乙区に金融機関等が抵当権などの設定登記をすることが目的であり実は登記そのものが所有者の本来の目的である権利の保全というよりも金融機関の都合という事情があるわけです。 土地家屋調査士ADRは、以上に述べてきた建物表題登記と直ちに関わるものではありません。また、市民も一般的には徴税、課税と言ったことと境界問題を一緒に考えることは稀であると考えます。何故ならば、市民にとって境界紛争(問題)は徴税、課税と言ったことまで考えが及ばない事柄であり、むしろ現実的な不動産処理を実行した場合の「価格」(あまり現実的ではない)を強く意識している場合が圧倒的に多いのではないかと思います。 いずれにしろ、調査士ADRは調査士の歴史の中に無かったステージであると考えます。新たな調査士の歴史を創っていくぐらいの気持ちで取り組んで行きたいものだと感じています。 |